OPEN FARM
(Process Report)
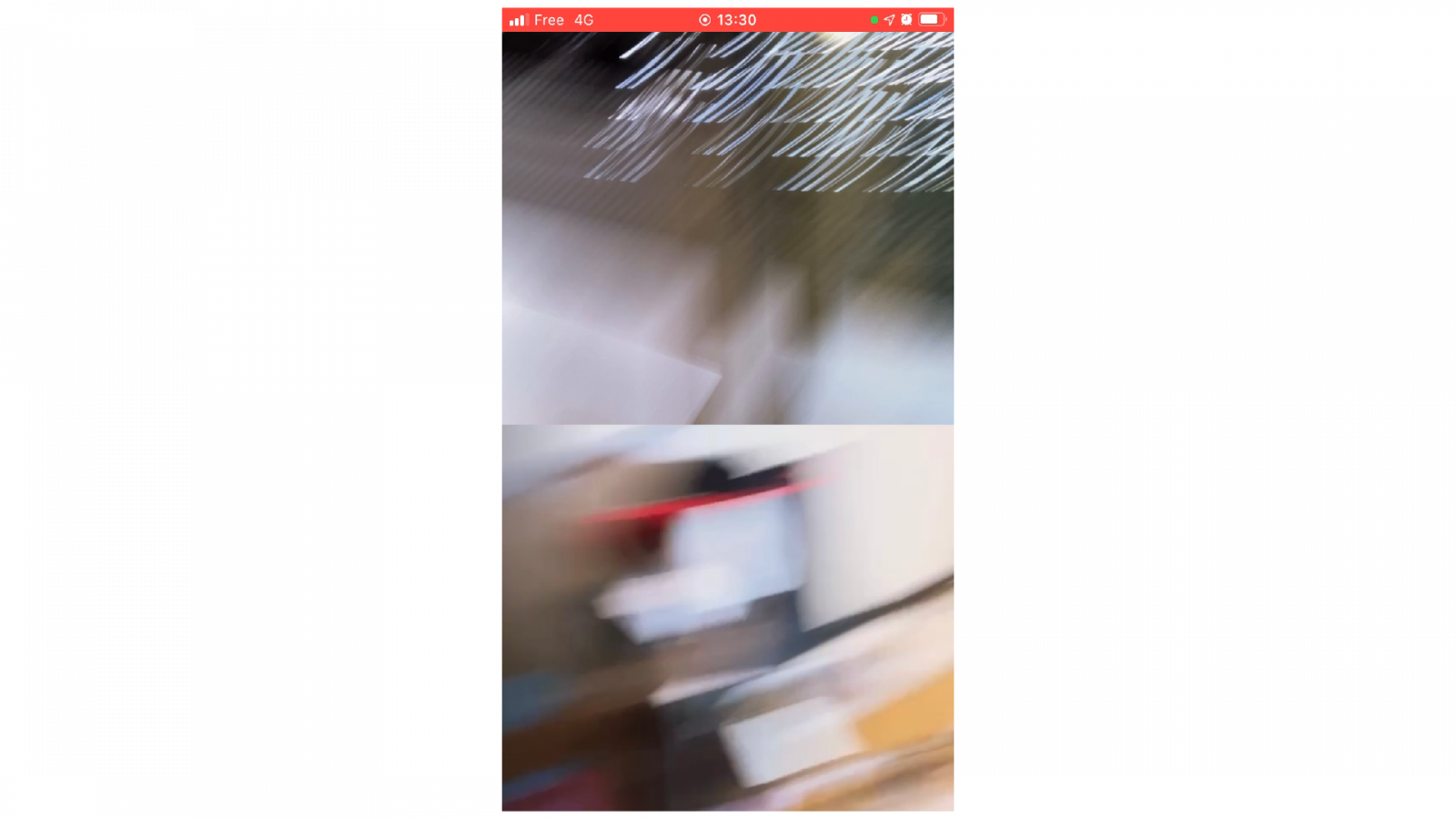
Farm-Lab Exhibition『unversed smash』成果発表(ワークインプログレス)レビュー
移動し、交換しあう身体のラリー
(取材・文:住吉智恵)
本年度、東京芸術祭ファームのプログラムのひとつである「Farm-Lab Exhibition」では、アジア全域から公募によってプログラムの参加者を決定し、夏から秋にかけて、オンラインのクリエイションと東京での滞在制作を重ねてきた。
ディレクションチームとして、フィリピンからネス・ロケ、日本から敷地理が参加し、共同で演出を担当した。またアジアを拠点に活動する若手アーティスト4名が出演者として、公募で選抜され、参加者全員で協働しながらクリエーションを進めていった。(Farm-Lab Exhibition『unversed smash』稽古場レポートはこちらから:https://tokyo-festival.jp/2021/openfarm_5)
本プログラムの成果発表として、10月29日から31日までの3日間、ワークインプログレスが一般公開され、初日29日の公演を観劇する機会を得た。

作品タイトルは『unversed smash』。「新しいスポーツをつくる」をテーマにパフォーマンスが展開される。人々が他者とのコミュニケーションを立ち上げ、親密さをつくり出す媒介としてきた事象の発展系ともいえるスポーツを、ここでは「ステイトメントのないパフォーマンス」と捉えている。
参加アーティストたちは、個々に異なる言語的・政治的・文化的バックグラウンドと視点を持ちながら、自他の垣根を越えて、動き・音・イメージ・オブジェクトなどの非言語的な交換「ラリー」を行う。さらにパフォーマンスを通じて、観客を含む他者の立ち位置を認め、その場にしかない関係性を立ち上げることを試みる。
本プログラムでは、東京芸術劇場B1Fのアトリエイーストとアトリエウエストの2会場が使われた。アトリエイーストはさしずめ「選手控え室」のような設定で、作品の導入部と終盤では、そこで行われている何やらチームの通過儀礼的行為を連想させるパフォーマンスの光景がリアルタイムで撮影される。
アトリエウエストには、微妙にスポーツ観戦らしい配置の観客用のベンチとフィールド(ステージ)が設けられている。来場者はそこで控え室から送られる謎のライブ映像を断片的に見せられつつ、目前で展開されるゲーム(パフォーマンス)を観戦することとなる。ここで行われる「新しいスポーツ」のルールは終始曖昧だが、ゲームの展開と共に、徐々に感覚的に理解するように促された。
4人のパフォーマーたちはバラバラの衣裳を着ていて、誰と誰が同じチームであるとか、敵と味方であるという設定は特になさそうだ。インドのチェンナイから参加したメロディ・ドルカスは、フェミニンなブラウスと身体にフィットしたスカートを身に着け、稽古場で見たときと同様、内に抱えた激しい感情と強い意思を抑制的に表現しようとしていた。インドネシアのパル/ジャカルタから参加したレウ・ウィジェは、シンプルな稽古着で、常に他のパフォーマーたちとの距離感をデリケートな仕草で探るような気遣いを感じさせる。インドネシアのバリ/ジャカルタから参加したオギは、ユニセックスなスポーツスタイルで、自身の体験に基づく身体の接触とケアへの探究を意識しているように感じた。日本の東京からは石田ミヲが参加し、リラックスした部屋着のなかで身体を泳がせ、多角的に意識を開放しようと試みる。
やがて4人がそれぞれ手や靴に仕込んだソックスを床に滑らせる「ラリー」が始まる。放られたソックスを放置したまま見つめたり、おもむろにキャッチして返したり、素早くカットインしたりと、選手たちの動きは緩急に富んでいる。ソックスはボールのような役割だが、スピードもバウンドもなく、ゴールがあるわけでもないので、丁々発止の快調な「ラリー」というよりは、むしろスローインとパス回しのやりとりがエンドレスに続いていく感じだ。
一方で、パフォーマーたちの母語と英語によるモノローグの音声が流れるなか、1対1の身体のコンタクトが展開されるシーンが随所に挿入される。クライマックスを迎えることなく収束したこのパフォーマンスのなかで、これらのシークエンスでは緊張と親密を行き来する濃厚な時間が流れた。稽古場を見学したときにも感じたことだが、異なるバックグラウンドを持つパフォーマーたちが、「初めて人の身体に触れるように」というディレクションを与えられて挑んだ身体感覚の交換は、スポーツの「ラリー」以上に鋭敏なテンションを伴うコミュニケーションとなったはずだ。

終演後にはじっくり時間をかけてフィードバックセッションが行われた。観客は「slido」というアプリを立ち上げて、匿名/記名を選び、その日の上演についてのコメントや質問を投稿することができる。集まったフィードバックをもとに、ディレクションチームが応答しトークを交わしていく(ファシリテーターは東京芸術祭ファームディレクターの多田淳之介が担当)。
このように観客から受けたフィードバックを随時生かしながら、作品をブラッシュアップしていくという研修合宿のような創作プロセスは画期的だ。ステップアップの過程が分解され、アーティストや制作者の体験に進行形で刻まれることによって、プロセスを反芻しながら次の創作につなげていくことが期待される。
例えば、初日のフィードバックでは以下のような質問が寄せられた。
「この作品を作り上げる中で、コロナの影響はどれくらい受けましたか? 人との交流、交錯が難しい状況だからこそ、身体的、言語双方の交流の意味を感じました」
「スポーツ/ゲームはやるものであると同時に観るものでもあると思いますが、観客についてどのように考えて作りましたか?」
「How do you think about ‘smells’ in communication? I am hesitant to y try ouch any socks, as it often smells bad. Smell is often associated with discrimination.」
「靴下は身体の一部なのか、異物なのか?」

ソックスの位置づけについての質問や所感は予想通りいくつも寄せられていたが、これについてディレクターの敷地が応答したコメントは大いに腑に落ちるものだった。
「ヴォルフガング・ティルマンスの写真作品のように、脱ぎ捨てられたソックスが単なる物としての靴下ではなくなる瞬間がある。そこには持ち主に対する感情などさまざまなものが残る。オブジェクトを交換することが身体性の拡張であることが、観客に伝わるように、しっかり見せようとした」(敷地)
現代美術の領域を起点に身体表現をスタートした敷地は、舞台作品における大道具・小道具という視点に違和感を感じてきたという。アートのインスタレーションのように、物(オブジェクト)と人(パフォーマー)の存在はフラットな関係性にあり、同じように大事なものとして扱われるべきだと捉えるからだ。
まさにそれはこの人材育成プログラムのねらいであり、本作のコンセプトの根幹にある「多様なコンテクスト上にある身体の等価性」と密接に関連する概念といえる。多様な身体がたえず移動し、ときには人間以外のものを交換するこのグローバル世界で、「遠くからこの場所に集まることの重みや質感」(敷地)を、へなりと投げ返されるソックスの存在を通して少しでも想像させることができたなら、このクリエイションはひとつの着地点を見出したといえるだろう。ソックスとパフォーマーを媒体として交換される「目に見えないもの」にこそ、重要な視点が隠されている。
Farm-Lab Exhibition プログラムの詳細はこちらから
https://tokyo-festival.jp/2021/farm_program/fle/
住吉智恵
アート・プロデューサー、ライター、Real Tokyoディレクター




