OPEN FARM
(Process Report)

対談:未来の舞台芸術を育てるために
多田淳之介(東京芸術祭ファーム ディレクター)
長島 確(同共同ディレクター)
アジアの若いアーティストの交流と成長の場として発展してきたAsian Performing Arts Farm(APAF)と国際舞台芸術祭フェスティバル/トーキョー(F/T)の研究開発、教育普及事業が合流し、あらたに誕生した「東京芸術祭ファーム」。今、東京の芸術祭で「育成」を推し進める背景と未来へ向けた展望をディレクターの多田淳之介、共同ディレクターの長島確に聞いた。
まずはAPAFとF/Tの研究開発・教育普及事業、それぞれの成果を踏まえ、あらたにファームとして出発することの意味や目標をお話ください。
多田 いちばん大きいのは「トランスフィールド」というひとつのテーマのもとで、芸術祭全体として、アーティストやスタッフ、それから学生も含めた若い世代の育成を考えていけるということです。もちろん、僕がディレクターになってからの3年間のAPAFだけでも達成できたことはたくさんあります。たとえば、一人のアーティストの価値観のもとに多国籍のキャスト、スタッフが集まるといった従来の国際コラボーレーションの方法ではなく、複数のディレクターをおいて、より多様なバックグラウンドが作品に反映されるようなつくり方にトライしたこと。また、去年初めてやったオンラインでのAPAF Labの最終プレゼンテーションも手応えがありました。ただ、その一方で、日本からの応募者が少ないという悩みもあったんです。英語が話せなかったり、そもそも国際的な活動に興味がなかったり……「どうして国籍やバックグラウンドの違う人と作品をつくるのか」というところから伝えていかないといけないという課題を感じてもいました。ですから、今回これまでF/Tや東京芸術祭プログラムが担当してきた学生向けの企画とも合流し、キャリアの初期やそれ以前から、国際的な活動を視野に入れてもらう場ができたことには、大きな価値を感じています。ここから将来のファームはもちろん、ほかの国際的なフェスティバルやプラットフォームのディレクターになる人が出てきてくれるといいですよね。

長島 今は演劇系の大学も育成機関として頑張っているし、平田オリザさんの無隣館、それからTPAM(現在のYPAM)のように、若い人たちが出会って、交流する環境もたくさんあります。ただ、そこからさらに一歩踏み出して、もっと、自力ではできないような出会いや経験をする機会があるといいなという思いは、ファームが立ち上がる以前のF/T時代からずっと持ち続けてきました。とはいえ、いきなり大きな国際協同制作の現場に参加するのはハードルが高い。APAFは、そのギャップを埋める取り組みでもあって、一方F/Tとしては、同じ芸術祭の仲間として、ここ数年は海外に限らず、リサーチをすること、ジャンルをまたぐこと、まちへ出ていくことを意識して活動してきました。それからもうひとつ大切だったのは、何かを試せる場を持つことです。作品をつくる前の緩衝地帯のようなものをどうプログラムに組み込んでいくか。こういった視点は、今回のファームを形づくるうえでも気にかけたことです。
芸術祭には非日常の、祝祭の場というイメージがあります。そこであえて育成プログラムを打ち出すことにはどんな意味がありますか。
長島 東京という都市は、「生産と消費」という視点から見れば、圧倒的に消費の場です。ですから、どこかでつくられた作品が一堂に会していて、それを鑑賞、消費するという芸術祭のあり方は、ある意味自然ともいえます。ただ、それだけでいいのかという疑問はF/Tをやりながらもずっと抱いていました。消費のスピードが速すぎて、つくり手もスタッフもお客さんも疲れているんじゃないか。僕自身もドラマトゥルクの仕事を通じて創作のプロセスのケアをしてきたこともあって、やっぱり作品をよくするためには、それが生まれる環境をよくしないとダメだと考えるようになりました。つまり、発表と消費の場としてだけでなく、生み出すこと自体をケアする機能を芸術祭が持つべきなんじゃないかと思ったんです。東京がポストオリンピックの段階に入り、なおかつコロナ禍で活動に制限がかかる中で、何に力を入れていくかといったら、それはやっぱり、人が育つチャンスをどうやって死守していくかだとも感じています。
ファームを貫くテーマ「トランスフィールド」は、地域や言語、ジャンルなど、あらゆる領域を横断していくという意味の造語です。単なる国際交流とは異なるその意義について、お二人はどう考えていますか。
多田 自分自身、演出家として、韓国や東南アジアの人たちと長く一緒にやってきたことの影響は大きいです。バックグラウンドの異なる人たち、それからダンサーやミュージシャンといった分野の違う人たちと仕事をするときもそうですが、違いを目の当たりにすることで、自分自身についてはもちろん他者や世界をとらえる解像度もあがり、一人では生まれなかったものが生まれてくるという実感を持っています。また、そういう経験を経て、日本の国内で演劇の俳優と作品をつくる時にも互いの違いを意識しながら、何が生み出せるのかを探れるようになりました。単純に作品が持つ視点も多様になり、届く射程も広がっていく、つまり作品が面白くなるのでおすすめです(笑)。それに、これからの日本で芸術活動するなら国内だけでは参照項が少ないんじゃないかと思います。国外にもヒントであったり、仲間がいることを知っているかどうかはとても大事です。
長島 そうですね。舞台芸術ってやっぱり集団創作ですから、他者を巻き込んで一緒にやっていかざるをえない。成果だけじゃなくそのプロセスをよりハッピーなものにするためにどうするのか。言語や文化の違う人たちと出会うことで、どうしてもそのことを考えざるをえない、ということの意味は大きいと思います。それと、僕は今、再生産の良さと狭さみたいなことをよく考えるんですよね。演劇だけを観て、演劇をつくっていくと、精度は高くなっていくけれど、ディテールにこだわりすぎてかえって視野が狭くなってしまうこともよくある。自分が取り組むジャンルについて学ぶのは大事なんだけれど、それと同時に、演劇じゃないものからアイデアや技術を移転させたり、あるいは逆に、演劇の技術を外へ持ち出すようなことするべきなんじゃないか。そうじゃないと、ジャンルとしてすごく高精度だけど、マニアのためだけの狭いものになっちゃう。そうならないためにも、さまざまな境界線をまたいで、いろいろな人と会って、いろんなことを考える、考えさせられる機会は必要だと思います。
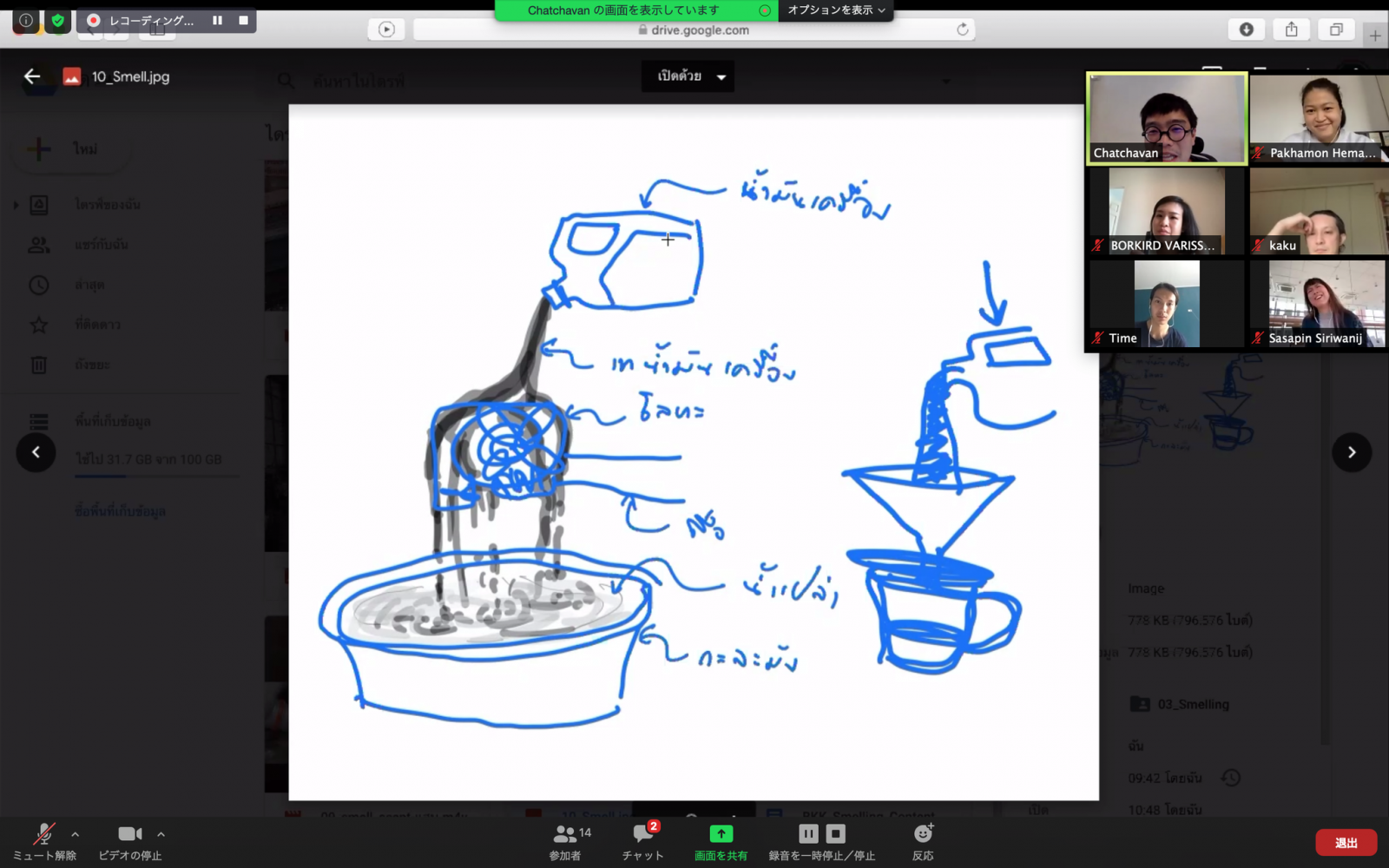
そうしたコンセプトが、つくり手向けの「ラボ」、制作者や現場に関わるスタッフを育てる「インターン」だけでなく、若い学生や観客を対象とした「スクール」までを包括するテーマになっているのも興味深いです。
長島 作品は観られることで、そのつど生まれるという側面もありますから、観る目の解像度も上がった方がいいと思います。でもそれは、批評家的な「プロ観客」を育てたいという意味ではないんです。これはまだファームの中でも明確にはなっていない、今後の宿題なんですが……観客の方々は「観客」として以外のアイデンティティを持っているはずで、それぞれの多様性を持ちながら作品と出会っているということについて、これからもっと考えてみたいと思っています。
今回のファームでは、多様なバックグラウンドを持つ人たちが協働するための「コミュニケーションガイドライン」も公開されました。
多田 このガイドラインはもともと、多国籍多文化の人たちが集まるAPAFの参加者、スタッフに向けてつくったものですが、それをファーム全体に適用していくことにしました。他者とかかわるのは、国際的な関係だけにとどまりませんから。
長島 作品をつくるプロセスは舞台裏の出来事であって、それは隠すものというような美意識はあってもいいと思います。ただその一方で、隠されている部分で搾取やハラスメントが起こっていないのかは、問われなきゃならないし、それが持続性にもつながるはずなんです。集団創作にはケア労働がつきものではありますが、ケアする側も含めて尊重され、守られる必要がある。そこを考え、現状を変えていくためにもこうしたガイドラインは必要だし、それを公開すること自体が希望のメッセージになればと思います。
多田 こういう取り組みは、僕らの世代の責務だと思ってます。今、ここで創作環境について考え、ハラスメントの防止もしていかないと、次の世代の人が入ってこないし、舞台芸術を志す人なんて増えませんよね。このガイドラインもそうですし、育成に力を入れるファームが生まれたこと自体も、芸術祭として変わりたい、新しい時代に進んでいきたいという意思表明として伝わるといいなと思います。

「都市の価値/Why Cities?」という年間テーマの背景にはどんな考えがありましたか。またそれはどのように各プログラムに反映されるのでしょう。
多田 プログラムごとにファシリテーターや参加者も変わるので、「具体的にそのテーマでリサーチをしてください」ということではなく、このキーワードをかたわらにおいて活動しながら、時々そこに立ち返ってみることで何が見えてくるのか、だと思っています。このコロナ禍を経て、人口の密集や経済をめぐる考え方は変わらざるをえないし、どこでどう暮らすのかについても考えざるをえなくなっている。東京の芸術祭のミッションとしても、しばらくは「都市」についてフォーカスしたいと思っています。
長島 英訳が問いかけになっているのも重要ですよね。「英語にするとき、Value of the Cityだとすでに価値づけがされている印象だから、問いかけの方がいい」というのは、インターンの枠をはじめ、さまざまな形でファームの企画に協力してくださっているArt Translators Collectiveのアイデアです。答えがひとつではない問いをキーワードにすることで、考えを膨らませたり広げたりするための出発点ができた気がします。
鑑賞プログラムに比べると、ファームの事業に実際に参加できる人はかなり限定されています。活動の一部を見学できるビジター制度も新設されましたが、今後どのように、参加者ではない人たちとプロジェクトの意義を共有しようと考えていますか。
多田 1年に1回も病院に行かない人はたくさんいるけど、みんな病院のことは大切に思っている。それと近い感覚になるといいなと思います。今でもFARM-Lab Exhibitionの成果発表は、トライアル公演としてアクセスしやすいはずですし、お客さんからのフィードバックの時間を長くとっています。そうした場を体験した方から波及効果が広がることを期待しています。また、ファームから出た作品が芸術祭で上演されるといったことも接点のひとつだと思っています。「あのファームがあるからこのプログラムがある、この人もあの人も実はファームを経験している、だから大事なんだ」というような感覚です。
長島 参加者にしてもビジターにしても、鑑賞したり、体験することがゴールじゃなくて、そこを通過したことで得た知識や技術をその先でどう使っていってくれるかが大事だと思います。そういう意味では、ファームから広がっていくものについては、こちらとしての希望や期待はありつつも、もう少し先を見ていかないと語れないなとは思います。

新たなスタートを切ったばかりではありますが、今後のファームの展望について聞かせてください。
多田 作品をつくる人だけでなく、各セクションのスタッフや関係者も含めて、総合的に育成できるような環境を考えられたらいいなとは思っています。たとえばアートトランスレーター・アシスタントでは、昨年の参加者が今年は正式な通訳としていてくれたり、トライアルの場が人を育てているという実感を得られています。ですから、同じようなことが、美術家やライターではありうるのか、といったことは考えます。また、舞台芸術自体を拡張していくような動きをもっとはっきり見せたいという気持ちもあります。
長島 単年度でなく、数年間続けてみることに意味があると思っています。本当は今に始まったことではないんですが、社会のいたるところでこれまでのやり方、考え方が通用しなくなる時代にわれわれは入っています。そこにパンデミックまで加わって、この先、その仕組みや考え方を変えていかざるをえない。舞台芸術も例外ではありません。これは良いほうに変わるチャンスでもあるわけですが、じゃあ、どうしたらいいのか。その答えは多田さんも僕も、たぶん誰も持っていなくて、本当にトライアンドエラーで見つけていくしかない。そのための協働の場としてファームに機能してほしいし、参加する人たちには、それを使い切ってほしいと思っています。
(取材・構成:鈴木理映子)
鈴木理映子
編集者、ライター。演劇情報誌「シアターガイド」編集部を経て、2009年よりフリーランスとして、舞台芸術関連の原稿執筆、冊子、書籍の編集を手がける。成蹊大学文学部芸術文化行政コース非常勤講師。【共編著】『<現代演劇>のレッスン』(フィルムアート社)【共著】「翻訳ミュージカルの歴史」(『戦後ミュージカルの展開』森話社)、「漫画と演劇」(『演劇とメディアの二十世紀』森話社)【監修】『日本の演劇公演と劇評目録1980〜2018年』(日外アソシエーツ)、ウェブサイト「ACL現代演劇批評アーカイブ」(*メンテナンス中)

多田淳之介(共同ディレクター/ファームディレクター)
1976 年生まれ。演出家。東京デスロック主宰。古典から現代戯曲、ダンス、パフォーマンス作品まで現代社会の当事者性をフォーカスしアクチュアルに作品を立ち上げる。子どもや演劇を専門としない人とのワークショップや創作、韓国、東南アジアとの海外コラボレーションなど、演劇の協働力を基にボーダーレスに活動する。2010年より富士見市民文化会館キラリふじみ芸術監督に公立劇場演劇部門の芸術監督として国内歴代最年少で就任、2019年3月まで3期9年務める。2014年「가모메 カルメギ」が韓国の第50回東亜演劇賞演出賞を外国人として初受賞。2019年東アジア文化都市2019豊島舞台芸術部門事業ディレクター。青年団演出部。四国学院大学、女子美術大学非常勤講師。

長島確(副総合ディレクター/ファーム共同ディレクター)
ドラマトゥルク。立教大学文学部フランス文学科卒。大学院在学中、ベケットの後期散文作品を研究・翻訳するかたわら、字幕オペレーター、上演台本の翻訳者として演劇に関わる。その後、日本におけるドラマトゥルクの草分けとして、さまざまな演出家や振付家の作品に参加。近年はアートプロジェクトにも積極的に関わる。参加した主な劇場作品に『アトミック・サバイバー』(阿部初美演出)、『4.48 サイコシス』(飴屋法水演出)、『フィガロの結婚』(菅尾友演出)、『効率学のススメ』(ジョン・マグラー演出)、『DOUBLE TOMORROW』(ファビアン・プリオヴィル演出)ほか。主な劇場外での作品・プロジェクトに「アトレウス家」シリーズ、『長島確のつくりかた研究所』(ともに東京アートポイント計画)、「ザ・ワールド」(大橋可也&ダンサーズ)、『←(やじるし)』(さいたまトリエンナーレ 2016、さいたま国際芸術祭2020)、『半七半八』(中野成樹+フランケンズ)、『まちと劇場の技技(わざわざ)交換所』(穂の国とよはし芸術劇場PLAT)など。訳書に『新訳ベケット戯曲全集』(監修・共訳)ほか。フェスティバル/トーキョー18〜20ディレクター。東京藝術大学音楽環境創造科特任教授。




