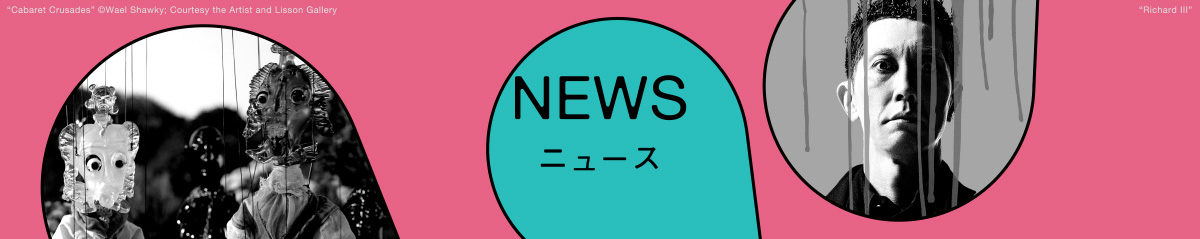
2018.01.12
《In Japanese only》『0場』第3夜(テーマ:社会と舞台芸術vol.1)イベントレポート
東京芸術祭2017のトークシリーズ『0場(ゼロバ)』、第3夜は12月5日に開催されました。アートという枠組みを超え、多様な分野で活躍する先端的なキーパーソンによる対話が繰り広げられる本シリーズ、今回のテーマは「社会と舞台芸術vol.1」。昨今、舞台芸術が劇場の“外”と関係を結ぶことが注目されるようになって久しく、東京芸術祭2017でも、劇場を飛び出し広場や公園で行われる演目が上演されましたが、このトークは、そもそも「外に出る」ことの意味や思想を考えてみる、再発見に溢れた場となりました。

登壇者は3名。日本におけるドラマトゥルクの草分けとして活躍、劇場の内外で行われる多くの作品に携わってきた長島確さん。都市やコミュニティに根差したアートプロジェクトの企画・制作を行う劇作家・石神夏希さん。そして、現代日本を代表する社会学者であり、SPAC‐静岡県舞台芸術センターで文芸部員も務める大澤真幸さん。アートを媒介として社会と接点をもつ2人に対し、歴史や宗教を含めた広範な知識と洞察で知られる大澤さんが論点を提示するという形で、ディスカッションは進められていきました。

トークはまず、石神さんと長島さんが劇場の“外”で手がけた作品やプロジェクトについて紹介することから始まりました。石神さんが紹介したプロジェクトは主にふたつで、ひとつは『ギブ・ミー・チョコレート!』という作品。横浜、フィリピン・マニラ、オーストラリア・メルボルンといった三都市で“上演”されてきた本作は、各都市で違いはあるものの、基本的には「指示書」をもらった観客が、日常の街のなかに溶け込んでいる「秘密結社」(!)のメンバーを探しに行くというもの。
石神さんの呼びかけにこたえた現地のコミュニティの人々が、街のなかに潜んでいる(=現地の人たちは、日常を暮らしている)、というわけです。合言葉や符牒となっている仕草でその人を探し出すとチョコレートや次の指示書をくれる、という楽しい仕組み。一方で、たとえば横浜ならばかつて終戦後に米軍に接収されていたという過去の記憶や、マニラではダンプサイトとして日々大きくなっていくゴミ山と共存する「パヤタス」という街のあり方、メルボルンならば多文化・多民族共生都市、という社会の様相を感じとることができるつくりになっています。
京都・舞鶴のアーティストインレジデンス(アーティストを現地に招聘、滞在制作をしてもらう事業)で取り組んだのは、『青に会う 2017.10-11』という作品。舞鶴に2週間滞在する架空の《青》という女性を基軸にしながら、毎日新たな戯曲を街のなかで“上演”するというものです。戯曲には《青》がまちで暮らす日常生活のほか、実際に舞鶴に住む人々と約束をして会って話すというような、その土地の人々との関係性が含みこまれており、人々は日々ウェブ上にアップされる戯曲のみならず、上演期間中に登場人物たちが記録した日記や写真などをたどり、滞在の終盤には自分も実際に「青に会う」ことさえできる、というものでした。石神さんは「演劇の“外”で劇作家として何ができるか」を問い続けているといいます。
長島さんの職業である「ドラマトゥルク」とは、近年日本でも注目を浴びている、劇作家や演出家と組み、リサーチなども行いながら、まさに作品と社会の“接点”を探る仕事です。そんな長島さんが自身のプロジェクトとして劇場の“外”で行ってきたのが、「アトレウス家」をめぐる一連のプロジェクト。
アトレウス家とはギリシア神話に出てくる、悲劇的な家族ですが、そのストーリーを実在の建築物と組み合わせてみることで、新たな発見を試みるという取り組みです。最初に行われたのは、『墨田区在住アトレウス家』。古い日本家屋に悲劇的なストーリーを組み込んだ瞬間、柱の傷やリフォームの跡など、かつてそこに実際に暮らした人々が残していった痕跡が、新鮮さをもって目にとまるようになったといいます。
転機が訪れたのは、次なる『豊島区在住アトレウス家』。東日本大震災を経て、悲劇を用いて家を面白がる方法に対して自問自答を重ねた長島さんは、雑司ヶ谷駅直結の区民センターで、会議室などの普通の部屋に観客が単に「いる」というあり方を模索します。具体的には、そこに寝床を用意して寝てもらう――つまりは「避難生活」の疑似体験です。実際の避難生活者の日々を体験するということではなく、東京都内であっても、いつでもどこでも「避難生活」の場になることを意識しながら、アトレウス家のストーリーを読む、という試みでした。火山の噴火によって自分の家から移らざるをえないという環境を日常として生きている土地で行われた『三宅島在住アトレウス家』も含め、「ギリシア悲劇の古典である戯曲をローカルな場と結びつけることで、日常の“見え方”が変わる」という演劇のあり方を、長島さんは探究してきたようです。

ここで大澤さんから、大きな問題提起がありました。そもそも現代日本において「演劇」本来の力がなかなか発揮されにくい状況があるのではないか、だからこそ石神さんと長島さんのような取り組みがクリティカルなのではないだろうか、というのです。
大澤さんの明晰な分析がつづきます。そもそも世界中のどこにでもある演劇の普遍性とは、何らかのパフォーマンスによって、「我々がこの世界に『いる』」ということを神々から承認してもらうという機能にある、と大澤さんはいいます。その「神々」が「観客」へと変わっていったのが演劇の歴史的な歩みであり、演劇本来の姿とは、パフォーマーとそれを見る観客が合わさることによって、「我々が世界に接している」ことを確認するひとつの様式だったはずだ、ということなのです。
しかし日本においては、近代化のなかで人々が伝統と切り離され、また演劇自体も多様な「趣味」のひとつの領域に入っていってしまうことで、演劇は「世界との接点をつくる」という本来の機能を失ってしまっている、というのが大澤さんの見解のようです。
これは非常に根本的な問題です。大澤さんは冷静な分析を経て、会場に熱い鼓舞をおくります。演劇のない社会なんてない。再び演劇を、本当に力のある表現にするためには、「これはすべての人にとって見るに値する」という必然性を打ち出し、その必要性に演劇人は応えないといけないのではないか――。特にSNSの普及以降、人々の日常的な振る舞いこそがどこか「演劇的」な色合いを帯びてきた現在、上演される演劇との“差”は少なくなってきてしまっている、という状況もあります。そんななか、石神さんと長島さんは「我々が世界に『いる』」という、人間と世界の“接点”を、それぞれ独自のやり方で取り戻そうとしている、と大澤さんは語りました。
この問題提起を経た石神さんと長島さんは、それぞれ立場や手法は異なりながらも、演劇は「居場所」に密接にかかわっている、と応答しました。地域のなかで行われるプロジェクトにおいて「自分はどこにいればいいのか」という問いを考え、観客や作品を介して「私はここにいていいのかどうか」を確認するということ――今後、さらに多くの人々が行き来するようになるであろう東京における芸術祭においても、こうした「居場所」の問題は、重要なポイントになりそうです。大澤さんがいうように、「自分がひとつのコミュニティに参加している」という、現代において希薄な感覚を、多種多様な人たちと一緒に取り戻すことができるのか。「演劇」の力は、いまこそ必要とされているようです。

